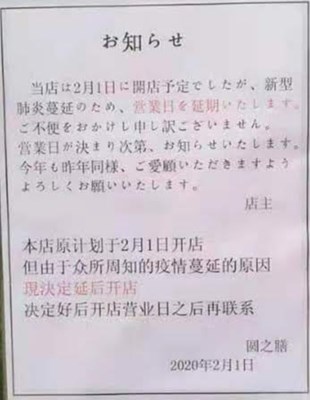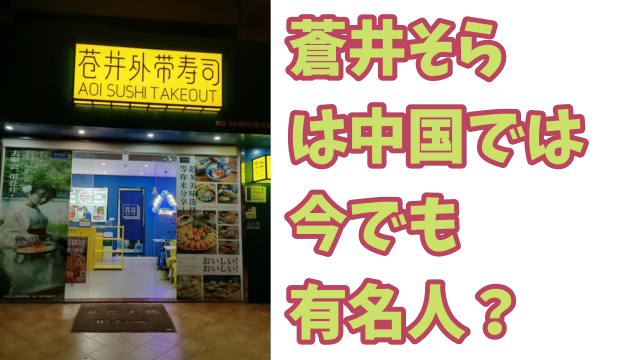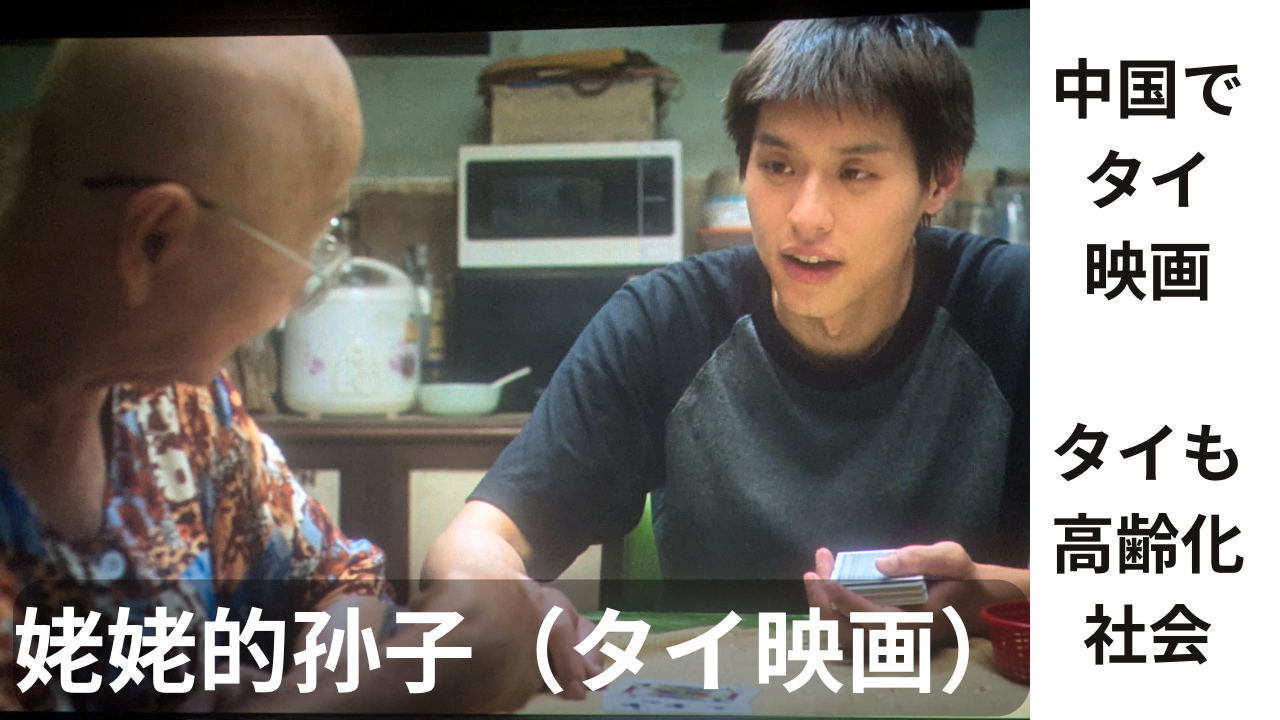2020年はコロナの影響で開催できませんでしたが、2021年は開催しています。今回が今年三回目の開催です。次回は9月に開催です。
1990年代に日本の澁谷工業株式会社勤務中に現場での小集団改善活動の一環として、毎週一回、1時間職場で勤務時間中に小集団活動を開催していました。当時は基本的に現場主体での活動です。
場所は変わって、中国でもこのような活動に参加できるということは懐かしくもあります。
中国と日本では環境も人も違うので、改善活動のやり方、考え方が違うと感じていますが、目的は同じです。
以前、S社の現場管理者の人が言っていたことを今になって思い出します。
彼は「中国では現場での改善活動が根付かない」 と言っていました。
この話は20年前に実際に聞いた話です。
今現在は2021年です。本当に根付かないのは現場のせいではなくて、工場の管理者が教えていないからだと思います。これは日本でも同じ。大手の会社であれば、ちゃんと時間をとって、泊りがけで合宿などに行き、社内の専門家(間接人員)の人たちが講師となって、細かく教える。
逆に中小企業では上の人達が、しっかりと教えていない場合が多いと思う。なぜ、教えることができないのか?間接人員がいないからだとも言えます。間接人員がいないのはぎりぎりで経営しているからかもしれません。
いいか悪いかは別にして、実際に実行・アクションするのはいいことだと私は思う。
何も動かなければ、結果も出ません。何か動けば結果が出ます。
私が以前、小集団活動で勉強した用語↓
アメリカのテイラーさん、ウエスタンエレクトリック、デミング、PDCAサイクル(デミングサイクル)、4M、QC七つ道具、パレート図、特性要因図(ゴジラの骨、むかしはこう呼ばれていた。)BS法(人の意見を否定しない。)科学的管理方法、、、、、、いろいろな言葉が出てくるが、英語からの言葉が多いように思う。
ウエスタンエレクトリック社のホーソン工場は経営学のケーススタディで研究している学者さんが未だに沢山いると聞きます。ここからアメリカの経営心理学が出発した語った学者さんもいるらしい。
ホーソン効果といわれており、関係書籍なども出版されている。
私が学生時代にホーソン効果を熱く語ってくれた中村君は滋賀県長浜にいるのだろうか?
時々、彼のことを思い出します。
経営と心理学を合体させるのは既存のドイツ式経営学(会計主体)とは違う新しい学問らしい。
経営と心理学を同時に語るのはもう何でもありなのかも知れません。文系も理系もなく総合的に語られるべき事象だと思います。ということは明確な答えが無いということだと思う。理系的考えならば、明確な答えが有る。
中国の製造業がこれから台頭してくる。(既にもう台頭して日本とアメリカを追い越している?)
もしかしたら、製造改善用語も中国語から出てくる時代が来ているのかもしれない。
中国の製造業無しに世界の製造業はかたることができないと言われている。
それだけ、中国製造業の影響力が大きくなっているということ。
私が今いるのは中国。中国には中国人が納得する最適な管理手法があるのかもしれないと日々考えています。






徐さんも真剣に取り組んでいる。 



次回9月開催会社の総経理のお言葉 
李部長は熱く語っている。
↑は改善交流会の動画です。動画のほうが改善交流会の情況がわかります。
ちなみにその後、珠海市内で一泊しました。その時の状況=>https://naokisu.com/?p=4032