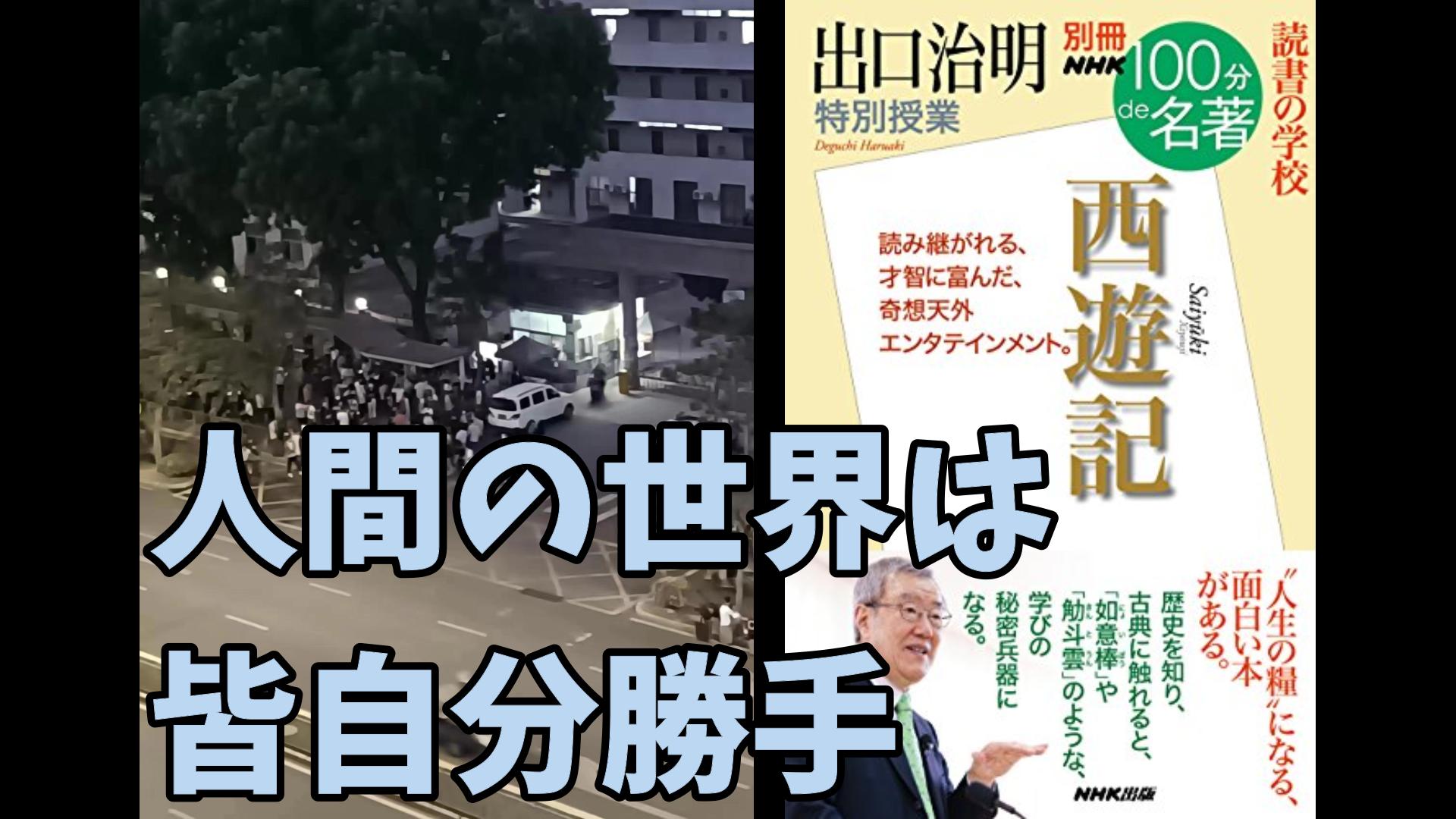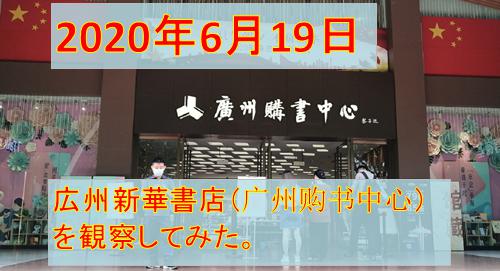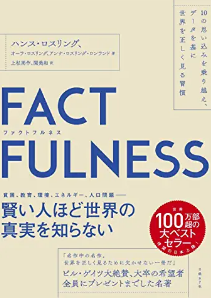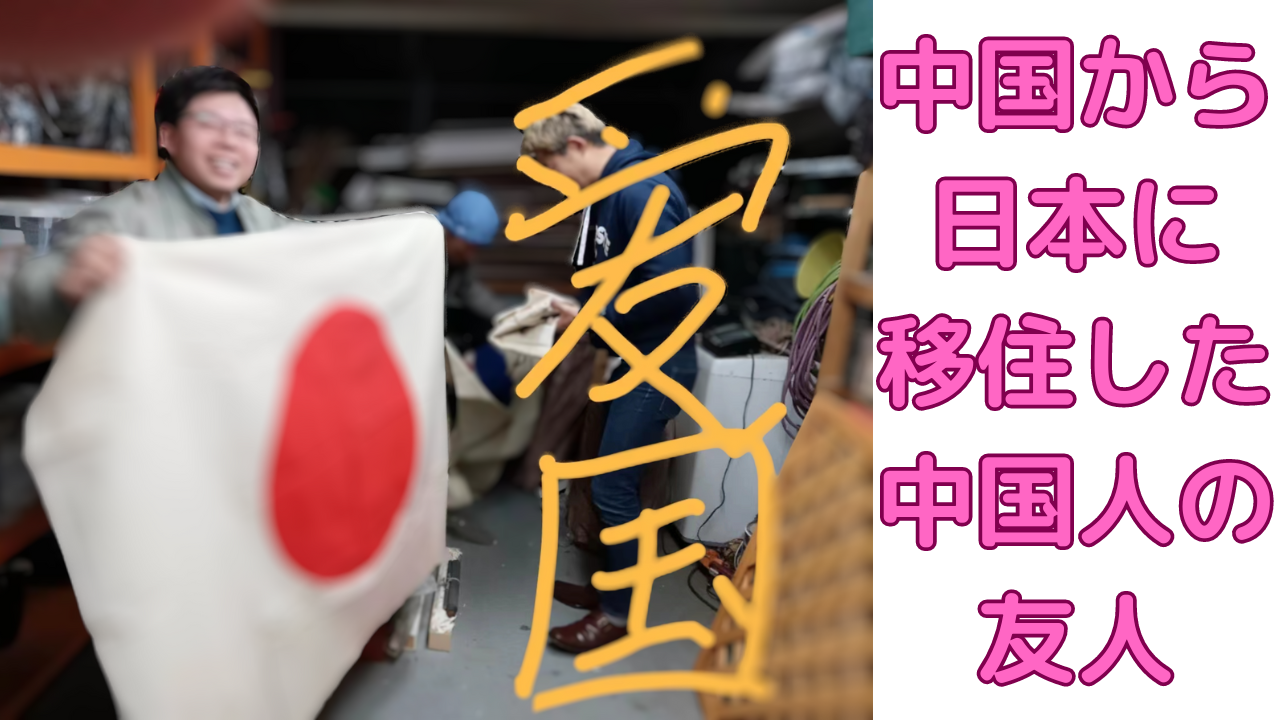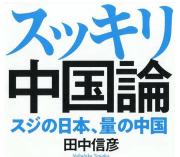
いろいろな中国論の書籍が販売されているが、この本の著者は中国で生活、仕事をして現場で体験したことをわかりやすく説明してくれている。中国で仕事をしている日本人は中国だけで約12万人いる。(外務省データ)
この書籍では明解に中国のことを述べている。
中国は量で判断
日本は道徳、スジ、規定で判断
私が30代のころ48歳の日本人と仕事をする機会に恵まれたことがあります。
残念ですが、その方は肝臓が悪くて5年前にお亡くなりになられました。その方がよく言っていたのは、「スジ」を通すということでした。この書籍で記載されていることと全く同じです。工場で品質関係の仕事をしていると日本人と中国人の考え方の差異に毎日疲れてしまいます。しかし、この本で説明されている内容を読んで100%納得できました。やはり著者も中国で実際に仕事をしていたからだと思います。
公平な立場で見て、どちらが良いとは言えません。しかし、2019年現在では量で物事を判断することも悪くはないと思います。
下記写真は中国高速鉄道駅(新幹線駅)での切符売場の状況です。皆窓口で一列に並んで切符を購入していますが、よく見ると一人だけ、割り込み(插队)している人がいます。しかし、皆とくに注意している人はいません。これが、何十人も割り込みする人がいた場合は時間が遅れるので、注意するのでしょうが、一人ぐらいであれば、注意はしません。なぜなら、大きな違いはないからです。日本国内であればたとえ一人であっても割り込みは道徳観から許されないかもしれません。果たして、どちらが合理的で正しいのか?双方の価値観が違うので、どちらが正しいかはわかりませ。事実、このことは中国社会では許されてしまうのです。「郷に入っては郷に従え」(入乡随俗)です。中国ではこれは問題ではありません。
この本は私の師匠であるK先生から紹介されて、すぐに日本から取寄せて読みました。Chinaを理解するために必要な本です。

中国で生活していて以前から思っていたことがあります。それは経済学の効用関数の考え方です。
引用始まり(Wikipediaより)
効用(こうよう、英: utility)とは、経済学の基本的概念であり、各消費者がある財やサービスを消費することによって得ることができる主観的な満足・欲望充足(への貢献)の度合いのこと。 所与の選好関係 に対して ならば を満たす実数値関数 の値である。
引用終わり
日本と中国では効用関数の式(Function)が違うということです。中国に対しては質よりも量の方が満足すると大雑把に私は捉えています。話が飛躍するかのしれませんが、少ないもの、小さいものよりも多いもの、大きいものの方が好まれる、満足してくれると思います。大雑把な捉え方で異論もあるかと思いますが、これは私個人の考えです。